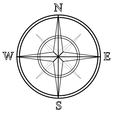・文学から生まれる科学(数学編)
これから、お話する内容は、どちらかというと、概念的のことと考えられます。
本当は、文学での表現を試みたいのですが、
小説と 思われてしまいますので、ちょっと長い文章を 考えられてしまうことが懸念されます。ですので、ここでは、説明を考えて、行きたいと思います。
<アウトライン>
数のことを考える時、
ここでは、数学と音楽の関係からはじめて行きたいと
思います。
というのは、数とは、科学の昔からの思想のため、世界を起源から説明する科学を語ろうとすれば、それは たぶん、世界(宇宙)の起源、生命の言及を必要とするためと考えられます。すると、宇宙の誕生、命の起源とは、”音(音楽)”が深く関わってきたと言えると思います。(人が存在するとき、声を聴くことなどができなければ、寂しいのではないか と、思います。)ここで、数の起源は、音楽であったのではないか、ということから説明することとします。また、それが音階・音程の演奏とそれを創っていくアイデアを、数学的に統制の採れた天体術理論を採用することで、音の周波数(音程・音階)と音響心理学的とを結びつけ、まずは聴覚を使い、
”数”概念を考えていきたいと思います。
次、”数”とは、(精神的・科学的)天文学などで、一番つよく育まれてきたことを明らかとすることで、これが未来”予測”(気象・天候予測)や宇宙論など
”人生哲学”などで用いられてきた(というより、これらを考えることで形作られてきた)ことを話すことが出来ればと思います。ここから、数で、人間の身体の部位の数(指の数)や長さなど、等身大の人間を尺度で世界を推量されてきたことや、文化(いろいろな物理的・心理的な”分量”を考えるための”さじ加減”など)を考えることより数学は一般化されていったのではないか、ということの説明を出来れば、と思っています。
では、以下、説明を試みていきたいと思います。
<数学と音楽の関係>
ここでは、数学と音楽の関係を見ていきたいと思います。さきほど書いたのですが、数とは、科学の原思想であり、世界を起源から説明するとき、おそらく、世界(宇宙)の起源、生命の言及を必要とすると考えられます。宇宙の誕生、命の起源とは、”音(音楽)”が深く関わってきたと思います。
ここで、音階・音程の演奏とそれを創っていくアイデアを見ていきたいと思います。
音階は、だいたい、ドレミファソラシという、7音を1インターバルで、周期率を形作っていると考えられます。
ドレミファソラシという命名は、きちんと世界観があるようです。
それを表すと次みたいとなって来ます。
音階 命名 意味 数とその意味解釈
ド(Do):Dominus, God in Humanity 1(創造)
レ(Re):Regina Coeli, Queen of Heaven The Moon 2(感受)
ミ(Mi):Microcosmos, Small Universe The Earth 3(生命)
ファ(Fa):Fatus, Fate The Planets 4(現実界)
ソ(So):Sol, The Sun 5(回復)
ラ(La):Via Lactae, Milky Way 6(調和)
シ(Si):Sidereal, Stars All Galaxies 7(精神)
(Wieder, Dr. June Leslie.著 「Song Of The Spine」などより抜粋)
この、音階は、きちんと意味と世界観がつくられていて、これは音の周波数と心理音響効果がつながって行くためと考えられます。また、これ以上は触れませんが、音の周波数(音階)と心理的効果(意味)は、身体のシステム(天文心理学)の形づくられて行くことで、これは生命が受け継いできた世界(宇宙)の歴史を反映されたこと と考えられます。この形づくって行くことは次で、ちょっとご紹介を出来ればと思います。(これらの観方を習得すると、音感が自然と身となって来て、ピアノを弾くことが出来ると、考えられます。)
まずは聴覚よりの”数”概念を考えていくことができたと思います。
<数と天文学>
”数”とは、(精神的・科学的)天文学などで、一番つよく育まれてきたと考えられます。
というのは、人・生き物のバイオリズムというのは、月や太陽などの運行で、昼夜や、”季節”に色濃く反映されたことであり、これで生死など左右されているためです。また、生き物、地球上の現象にバイオリズムがあるため、”事物の周期を計算する”という考えが必要となってきます。(天文術の起源)対象の周期や同期を調べる時、例えば、バイオリズム2年と3年の生き物が、この”鉢合わせ”(最悪な状況となって行く)の周期は2×3=6年ということが予測されます。一方、バイオリズム2年と4年の生き物が、この”鉢合わせ”な周期は4年です。このため、素数のバイオリズム周期を持つ生き物は生存期間が一番長いこととなって来ます。(つまりこのため、自然界では、素数というのが大変な意味を持つこととなって来ます。)また、地球に住んでいる限り、このバイオリズムなどで、さまざまな天変地異を克服されてきた証拠の一つで、農業というのが生まれたことが考えられます。農業とは、気候変動に対応するため生み出された食料確保の手段だったのではないかと考えられます。
(参考URL:「人類はなぜ農業を始めたのか」
https://www.nagaitoshiya.com/ja/2001/neolithic-agriculture/)
また、このような自然界のバイオリズムを克服する手段である天文学の起源で、
シュメール(メソポタミア)文明、マヤ文明などでは、60進法が使われ、これが天文学で優れ、太陽の観測など、一年間の長さなどは正確に365.242日と驚くほどの精度で用いられていたそうです。
(参考URL:「シュメール人はなぜ六十進法を用いたのか」
https://www.nagaitoshiya.com/ja/2013/sexagesimal/)
このように、数は、いちばん、天文学に関わって、発展してきたと考えられます。
<数と文化>
ひとは、数で、人間の身体の部位の数(指の数、関節の数)や長さなど、等身大の人間を尺度で世界を推量することが出来たと、考えられます。数は、1~10まで で、手・足の指の数が合計10本の ためと考えられます。これが10進法の起源と言われています。(参考:シュメール(メソポタミア)文明、マヤ文明では、60進法(1~60まで数えてはじめて、桁(位)が上がる数え方)が使われていたと考えられています。)
また、人間の身体の長さを尺度で観た時、次のようなことが言葉となっています。
●束(つか)・・・小指から人差指までの甲の幅。
●尺(しゃく)・・親指と人差指を伸ばした長さ。しゃくとり虫の要領で木の円周
も測れる。一束の二倍。現在の尺はそれより長くって30.3cm。
肘から手首までの長さ、尺骨に相当。
●丈(たけ)・・・身長。一尺の十倍。
●尋(ひろ)・・・両手を広げた長さ。丈と同じ長さ。
●歩(ぶ) ・・・三歩、歩いた距離。一丈と同じ長さ。畳を三歩で歩く作法は、
ここが出発点。一歩(ぶ)の60倍が一町。36町が一里。
(「身体数寄」さんより抜粋
http://nakaemon.blog67.fc2.com/blog-entry-36.html)
この、何を”物差し”とするかで、世界は大きく変わって来ると考えられます。これらで、優劣はなく、土地土地の文化で育れて来たこと と考えられます。現在の科学の世界では、SI単位系(いわゆる、グラム、秒、メートルなど)で測量されますが、これらは、10進法などの世界観で表現されています。1グラムというのは、1ml(cm3:立方センチメートル)の水の重さ。1秒というのは、1年を365日(12月間)、1日を24時間、1時間を60分、1分を60秒と、きちんと既述の世界の天文学と数で述た世界観の反映をされています。1メートルは、
本来は、地球の赤道と北極点の間の海抜ゼロにおける子午線弧(地球表面を縦に結んだ)長を 1/10000000 倍(1千万分の一)と考えた長さを意図されたことと考えられます。いま現在の単位というのは、世界の文化の尺度など継承されてきていると考えられます。
次、文化を考えることより数学は一般化されていったと考えれられます。というのは、いろいろの物理・心理での”分量”を考えるための”さじ加減”などは、いまお話出来たのと同じ、尺度が人の身体を生地と考えて作られたことなど、考えられます(物理での解釈です)また、心理での”分量”を考える時、”さじ加減”という言葉では、ちからの入れ具合、体調の具合、料理での味加減など、これらの尺度で違いが見えると思えますが、この”物差し”の種類のことでは、鋳型、思われます。
数学、この数というのは、無理やり作り出されたことなのではなく、いろいろの 人達の 文化で色濃く形づくられて来たことで、これらのこと と、発展されてきた、と考えられるのではないか と、思われます。
熱(伝導)の解析数学で、この伝わり方を数学で厳密な(分方程式の基で)解析をすると、この解は、周期関数(sinθ、cosθ)の”生地を加え合う”ことで表されうるという考えを発明された方です。遠く限りなく延びていく周期関数という、”場”を表現する数式を(たくさん)集すことで、どの関数(直線含め)などを再現できるということを、数学で厳密な証明をされた方です。(つまり、宇宙は果つ こと の ない、すべて繋がっている、巡り行く、という世界を直観的に見抜き、これを数式で厳密、再現・表現されたのではないかと、考えられます。)また、これは現在のさまざま の分野の科学で、熱の以外、様々の方程式の解で用いられています。
フランス生まれで、7歳の時、両親を失い、修道士の愛護で貧しい
生活を送っていました。少年の頃より、数学を愛読されていましたが、フランス革命で、革命政府の作った科学校の学人を行くことで人生が変わります。
ナポレオンのエジプト総督まで と、ロゼッタ・ストーンを母国へ持ち帰り、
エジプト文明の解読で、シャンポリオンと道を切り開きます。
この後、”熱(重力と並んで物質の二大要素になる性質)”の伝導法則を
研究され、方程式論や方程式の数値解法の研究を行い、いまで言う、”次元”解析を考えついたと考えられます。
彼の発明されたフーリエ解析法は、今日では、微分方程式を解くための極めて強力な手法で、この、物理学や工学で、光や音、振動、コンピュータグラフィックスなど幅広い分野で、なくてはならない技術と考えられて用いられています。
(スペクトル(周波数)という概念など、彼がつよく考えたのではないか、と考えられます。周波数次元解析と、つないで行く と、考えられます。)
自身、幸せなこと、両親を失ってはいないのですが、
つないで行くことの道を教えて下さる人と、思われます。
数学、数式を理解する時、欠くことの出来ないことを順で説明すると、次のとおりとなって来ます。
①四則演算(-、+、÷、×)の概念とその起源
②四則演算の応用
③数式を用いた未知分析の手法
④未知分析を考える
では、以下、順、説明を出来ればと思います。
①四則演算(-、+、÷、×)の概念とその起源
”-、+”とは、”数える、測る”という行為から始まった。そのため、時間変化、空間差異で、現象の”変化”を感じとったことを、感じた度合い(数値)で、表現された時や、同次元のことを足す時などで計算上考えられる、
”量的概念計算手法”などではないか と、考えられます。
”÷”とは、”等分する”という考えから始まった。そのため、÷の概念は、万人と平等で割り当てるという民主主義的な考え、また、等分するだけでなく、その因数分解(例:12=2×2×3の2、3,4という約数(質)を見つける手法)的な考えより、何か一番根底となっている主原因を割り出し、探っていく”質的概念、還元探索手法”などではないか と、考えられます。
”×”とは、”こと、の周期を計算する”という考えから始まった。そのため、×の概念は、対象の周期や同期を調べるのに使われます。(例:バイオリズム2年と3年の生き物が、その”鉢合わせ”になる周期は2×3=6年となって行くということ。(そのため、素数のバイオリズム周期を持つ生き物は生存期間が一番長いこと となって行く。(このため、自然界では、素数というのが、大変な意味を持つこととなって来ます。)))つまり、”×”とは、異なる”種類”のことを計算で一つの質的概念の量を創出する、”質的概念量計算創出手法”などではないか と、
考えられます。
②四則演算の応用
”-、+”は、量のことのみ扱えるため、単位の揃った(同じ質の)ことのみを、考えることとなって来ます。
”÷、×”は、量のことだけでなく、質のことなどを扱えるため、単位(質)を生み出すことができると考えられます。(ですが、同じ”質”であっても、”種類”(人)が違うことを足す(量で計算をする)時は、”-、+”を使います。)
つまり、大切のことは、”質”と”量”という2つの概念で、量を扱うとは、
”計算する”ということ。質を扱うとは”探求・創出する”ということ と、考えられます。
このため、質の種類のことを、数学では、”次元”と呼ぶと考えられます。
③数式を用いた未知分析の手法
ここまでで、未知分析の手法は、その質を”探求・創出する”ということから、”÷”、”×”の考え方に近いということがお分かりいただけたのではないか と、思われます。
未知分析は、探求する、直観・洞察力を使い見出す、という力を必要とすることが言えると考えられます。では、その洞察力を身とするため、どうすれば良いか、話て行ければと思います。
直観や洞察力というのは、様々のことを考えて見つけ出すということで、これを身とするのは、ここまで難しいことではないかと、思われます。
一番分かりやすく説明させていただくと、それは、こころと身体の遣い方の考えと帰着すると考えられます。
武術などでの、”こころと気”の遣い方がポイントだ、と考えられます。
方法で、意識と気を”下腹部”の一点とすること と、思われます。
この、”下腹部”の一点とすることより、こころと気を収底めて、意識が 通底することで、外の世界を繊細と つかんでいく基礎ができると考えられます。
この、意識と気を下腹部とすることで、外の世界などのことで、収底な状態を取ることができると考えられます。
ここより、外の世界や相手のことを考える時、対象者のバイオリズム(息遣い・脳波)をつかむことが重要と考えられます。この対象の波動をつかむため、自分の一番基底となっているバイオリズム(周波数)を、相手の周波数と同調(了解)することより、つかむことができると考えられます。(これを、当HPでは、
”無得然周波数(鼓動)を捉える”と考えています。)
この無得然周波数とは、呼吸・心臓・脳波のバイオリズム(周波数)が、”公約数”と考えている底の周波数のことを言います。つまり、根底でそれら3つの呼吸・心臓・脳波のバイオリズムをつないでいる、周波数(鼓動)のこと と考えられます。
この無得然周波数をつかむことで、様々のこと と、通じられるかな と、
思われます。
④未知分析に向けて
(おさらい)
数式、とくにそれの要素となる「数」は、”量”と”質”の二つの性質により作られています。
数式では、”=(イコール)”を含むため、その両辺および構成”数量”の数量は、それぞれ、同じ単位である必要があります。
10(個)=2(グラム)+3(秒)+5(メートル)
という計算は成り立ちません。そのため、
5(人)=1(人)+4(人)
というように、”人数”という”単位”の揃ったものである必要があります。(これを、数学では、”質的次元”を揃える、と言います。)
また、数式で用いられる、四則演算(-、+、÷、×)の概念は、
”-、+”とは、”数える、測る”という行為から始まった。そのため、時間変化、空間差異による、現象の”変化”を感受したものの、大きさを数値化した”同質なものについての量的計算測定手法”と考えられます。
”÷”とは、”等分する”という考えから始まった。そのため、民主主義的に等しく配分したり、因数分解により質を見つける、主原因を割り出し探っていくという”質的概念、還元探索手法”と考えられます。
”×”とは、”ものごとの周期を計算する”という考えから始まった。そのため、各生物のバイオリズムの最小公倍数を求めることで、様々な生物が最悪な状況に陥る時期を予測するという、異なる”種類(生物)”のもの(バイオリズム周期)を計算して一つの質的概念の量を創出する”質的概念量計算創出手法”と考えられます。
こうして、数式、とくにそれの要素となる「数」および「四則演算」は、”量”と”質”の二つの性質を主軸にして、計算式の中に組み込まれることになると考えられます。
(数式応用編(未知分析方法論))
未知分析を行うにあたり、前回では、その人の”基底周波数(最も根底を流れている身体バイオリズム(心臓の周波数など))”に、同調させる(割り出していく)ことで読み取り、その人の根幹となる”息遣い”を探るという方法をご説明させていただきました。
ここでは、そのように基底周波数を、”気”を用いることにより読み取っていくことで、その人の”エネルギー(真剣さ)”というものを解析していく手法をお話しさせていただければと思います。
これは、数学で言えば、多変量解析という手法に当たると考えられますが、これを、やさしく紐解いていきたいと思います。
対象となるものの”エネルギー(真剣さ):量”をEとした時、そのパワーを単位(質)として数式で解析すると、
E=X+Y+Z+W+・・・
(<変数(要素)> X:気、Y:様子、Z:表情、W:性格、、、)
というようにでも表せると思います。
(ここでは、”こころ、気”を遣って、その人のエネルギーを読み取っていった時に、気付く順に、X、Y、Z、W、、という要素を考えることにしました。)
また、E:真剣さ として考えると、
E=X+Y+Z+・・・
(<変数(要素)> X:行動力、Y:交渉力、Z:知識力、、、)
というように考えても分かりやすいかと思われます。
これを、一般式として当てはまるよう、解析しやすく表現し直すと、
E=ax+by+cz+・・・
(<変数(要素)> x:行動力変数、y:交渉力変数、
z:知識力変数、、、)
と表せると考えられます。ここでのa、b、cとは、x、y、zを質としてその大きさを測った時に、未知数となっている、その”力(質)”に対する”おもみ(係数)”です。
一般式における未知分析では、x、y、zなどの変数要素は、”こころ、気”により割り出し特定化させることで、”質(要素)”の変数値として見つけ出すことができ、その人の様子を、その時々において考えることで、それら質的要素の値も測定できると考えられます。
また、E:真剣さというのも、そのトータルな値も、”気”を遣うことで、その大きさを読み取る(初期段階で認知する)ことが出来るのではないかと思われます。
そうなると、a、b、cという”未知係数”を特定できれば、いかなる時でも、
x:行動力変数、y:交渉力変数、z:知識力変数 さえ読み取れれば、その時々での、対象者の真剣度(E)を導出できることになると考えられます。
(つまり、このa、b、cを特定するという行為が、未知分析によって、対象者の”未来予測”を可能にする、ということになると考えられます。)
この”a、b、cを特定する”には、何回か、その人の”E:(トータルな)真剣さ”、および”x、y、z:力変数”を読み取り、それらをトレースしていくことで
いくつもの E=ax+by+cz.. という方程式(数式)を立て、それらを連立して解く、ということで算出できることになると考えられます。
このようにして、未知変数は突き止められることになると考えられます。
(本来、多変量解析では、対象について、統計処理により連立方程式を立て、a、b、c:おもみ(係数)を算出します。今回は、”気”により直観的に、係数を”捉えていく”という方法を採りました。)
こうして、”気”を遣うことで、まず”質”となる変数を見つけ出し、対象者のその時々での”変数値”を測定し、各々、個別に、トレース、連立させることで、
”未知係数”を突き止める。そうして、未知変数解析を行うことで、数学的に値を用いて、未来予測を可能にする未知分析ができるようになると考えられます。
(※発展形として、この多変量解析法を微分方程式の形式で解析すると、今現在、活発に研究されているシステム現象解析に繋がっていくと考えられます。)