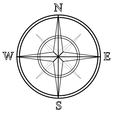ⅳ-②周波数(鼓動)体としての身体
前章で、対峙する他者との間でのやりとりを話すkとが出来たのですが、ここでは、つねに動的な状態の<いま>という瞬間を捉え、実際、どう考え、からだをつかっていけばよいのか、ちょっと具体で話てみたいと思います。自己の周波数は、
呼吸の周期、脳波の周期、これと心臓の鼓動周期と、三つの種類の周期を持つ体内周期活動波などが考えられます。
いろいろ の 活動波の周期は、座禅などをするとき、呼吸、心臓、脳波の順で この活動は活発と されて行くと考えられます。ですが、これらは、いろいろ と、はたらくのではなく、心臓の周期(鼓動)を”どだい”とすることで、呼吸の周期をコントロール、脳波の穏やかな活動を試みます。
それぞれの周期が最小公約数などと呼べるような同期を持って はたらくとき、これを、然々 まだまだ周波数を、つかんで行くと考えられると思います。自己を内観するときは、自分の呼吸の周波数を落ち着くのを考えて行けばよいと思うのですが、他者と対峙するときは相手の呼吸の周波数(鼓動)などを考えていくと、よい と思われます。
このため、他者と対峙するときの準備で、自己の呼吸をコントロール、
自身の体内の脳波や鼓動数を底とすると、よい と思われます。
この参考で、日本の武士の時代で行われていた能楽での、つづみを打つ周期がよい例などで挙げられると、思われます。能楽でのつづみは、その演者の無意識をいさめ、意識に隙を無くすよう打たれていると、思われます。
この無意識を意識下とすることで、ずっと動的な状態の<いま>を途切れることなく、つかんでいく、行為は、自己の然々 まだまだ周波数を捉え、他者と対峙するとき、その自己の内発力で、相手の周波数(鼓動)を捉え理解することができる土台となってくれると思われます。
これで、自己の鼓動の地平をつかみ、他者と向き合って行くことが出来て行く かな と、思われます。