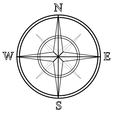ⅲ-⑤化け学
化け学は、この名の通り、身体や物質などが変化することを捉える学問だと思います。これは、自然の色、音(声)、形、香り、感じ、といった五感で感受される感性で、純粋なこころで感動するこころを考えて行くことで、
これがどう変わるのかを大事とする(理解する)という気持ち・思いから生まれたこと と、思っています。また、自然界の他、体内の状態を考えれば、薬学や医学などを考えて 頂けて行く こと が 出来て行く のではないか と、思われます。
ⅲ-⑥物理学
物理学は、この歴史で観れば、数学と同じく、物理方程式を考えることで、自然な法則と、なったと考えられると、思われます。作用・反作用の法則とは、(数学と同じく)ほかの余計なことをいっさい排除すると言うよりは、
(この根源的なことを具体的かつ精緻で捉えたとき考え出される)汲み取って行くこと の、物理的調動の通体態を、いうのではないかと思われます。言い方を変えれば、果つ こと の ない声を、汲み取り表現することなのではないか、と言えるのではないか と、思われます。このため、物理での微分(方程式)とは、意志の未来と働く向きのことを意味され、積分するとは、これまでの経験を汲み取り行くことを意味されるのではないか と、思われます。
ⅲ-⑦命 態体学
いろいろ の 考え で、自己(の体内)を内観するという こと が考えられると思われます。以前、お話出来たことで、いのち は、物質より、と 考えられます。ひと の からだは、血が通うことと、神経が通う(または気が通う)ことで、維持されると思われます。このため、自己の体内を内観するとき、これを精緻で把握すると、からだを微細と観て禅するということと言える、と思われます。
いろいろと感じられて行くのを把え、神経(または気)を通じて身体をコントロールする(身体の鼓動を捉えて、いろいろ と 考えて行く)ということ と、思われます。この こと で、いのち を 鼓動より捉えられるのではないか と、思われます。