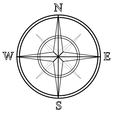Ⅰ.座禅
ⅰ.なぜ座禅をするのか
(手段としての座禅)
ⅱ.座禅の作法(組み方)
ⅲ.座禅
(こころを落ち着かせ、
ゆとりを生む方法)
Ⅱ.考え方
(本質の探し方)
ⅰ.直観的な捉え方
ⅱ.宗教的な考え方
ⅲ.学問的な考え方
Ⅲ.まなぶということ
(学習法,
座禅の”どだい”)
(底への到達)
ⅲ.鼓動との対話
ⅳ.身体との対話
(身体を充実化する)
(禅的感性)
ⅵ.自分と地平
ⅶ.自分らしく
Ⅲ-ⅶ.自分
ここでは、このⅢ章でお話したことをまとめ、どう自分で、自由で考えることができるか、総括することで終わりたいと思います。
座禅を組むことで、意識を<いま>で集中することで、よく、自身の内部と外部の状態を繊細く、
つかんでいきます。この時、観える根底(深さ)での世界と対話を行くことで、自身の心臓の鼓動を
つかんで、果つ こと と、されて行くため、この鼓動数を 自身と周囲の存在をより根本で基本を固めて行くことで、
然々 まだまだ周波数(鼓動数)を考えて行き、これより、自然と、外の周囲との事での ことを作って行くことができて行く かな と、思われます。この時、周りと、ちょうど よく調度された鼓動数の意識をつくり、
息をおいて、観て行くことで、このような状態で周囲との事で作られる
ことばを受け取り、見つけられる、ことができて行く かな と、思われます。
自分で、自由で考えられるとは、<いま>というかけがえのない瞬間をどう考えるか、考えられること の
出来る自分自身で考えられる自分自身の鼓動を見つけられ、
周囲との事で作られる言葉を受け取り生み出すこと かな と、思われます。この時、自分と思われるよう、
本来の自分や、他の自分を考えて行く ことが出来て行く かな と、思われます。