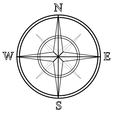Ⅰ.座禅
ⅰ.なぜ座禅をするのか
(手段としての座禅)
ⅱ.座禅の作法(組み方)
ⅲ.座禅
(こころを落ち着かせ、
ゆとりを生む方法)
Ⅱ.考え方
(本質の探し方)
ⅰ.直観的な捉え方
ⅱ.宗教的な考え方
ⅲ.学問的な考え方
Ⅲ.まなぶということ
(学習法,
座禅の”どだい”)
(底の到着)
ⅲ.鼓動との対話
ⅳ.身体との対話
(身体を充実化する)
(禅的感性)
ⅵ.自分とその地平
ⅶ.自分らしく
Ⅲ-ⅳ.身体との対話(身体を充実化する)
からだの鼓動との対話で、よい自分、否定的な自分などが観えて行くと思います。よい ところは受け取ればよく、否定的なことでは、程度で、理解していくことができたら、ここからは「思う こと を考えて、果つ こと を行く」
ということを考えるとよいと思います。
つまり、これを考えること で行くこと で は、
力で抑えようとするよりは、こころと身体の了解、調度役での意識が、たがい と、思う こと を、理解すると、
不思議と、こころとからだの間の葛藤が晴れると思います。
「思う こと を考え・たがい と交換的の理解をする」力と、ここから好転させていこうとするよい こと の部分とが
いろいろ と考えられて行く かたちを取って行くことができれば、
自然と、こころと身体が元気で行くことが出来て、理解力(たがい と考えて了解する力)を考えられること と、
考えられて行くのではないか と思います。
Ⅲ-ⅴ.まわりを感受する力(禅的感性)
前部までは、意識の内面を深くすることを考えてきたと思います。ここでは、そこで得られたこころと身体など、意識を、外のこと とを考え向けていこうとする段階のことのお話を出来ればと思います。
ここまで様々な意識を柔軟とすることができれば、ここより、外のことをどう考えていけばよいのかということ と思われます。ここで再び考えると、よいこと が、からだの鼓動のことです。鼓動は、この周波数(心臓の鼓動数)など や、この機能で、血および体温などの こと と、思われます。座禅を組んでいる時、周波数(鼓動)が関わって来ると思われます。(意識を果つ こと より される行為は、周波数(鼓動)を、意識の果つ こと となって行く、低周波の脳波(α波など)を考えていくこと と同義と思われます。)外を感受するとは、この身体の鼓動数を、外の出来事のこと と で、”どだい”を考えて行くこと と、思われます。”どだい”を、つないで行くことで、他者と対話する
こと より、はじまる と、思われます。 他者と、向き合うということ とは、自身の周波数(鼓動数)と、他者の周波数(鼓動数)と を 理解することで、気づいていくとよいのではないかなと思われます。つまり、自身と他者の鼓動数と、調和をとる(ちょうど、よい 一(ひと)息をおいて)ということ と思われます。(変えて言えば、他者と共存して行くという こと と思われます。)外の ことを、つないで行くため、他者と了解された鼓動数をつくれれば、
とても穏やかで、調和の とれた ことを感じられる と、思われます。